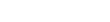- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
この東宝映画「弾痕」は、「狙撃」に続いて加山雄三が主演した、東宝ハードボイルド三部作の第2弾となる作品で、監督は「日本沈没」「八甲田山」の森谷司郎だ。
主人公の滝村憲(加山雄三)は、日米2つの国籍を持つ男であり、アメリカの情報機関のメンバーで射撃の名手だ。
彼は、米国特使の一行に特攻を試みるテロリストを、ヘリから狙撃し犯行を阻止したり、米国大使館に亡命を希望する中国の経済使節団のメンバーを保護したりと任務遂行に忙しかった。
そんなある日、彼は敵対する何者かに狙撃され、弾は近くにいた彫刻家・沙織(太地喜和子)を負傷させてしまう。彼女を助けた滝村は、彼女の作品のモデルとなり会合を重ねていく。
滝村は、日本海側から密入国を企む中国の工作船を迎撃、中国側は謎の武器商人トニー・ローズと東京で取引を企んでいた。滝村はこれを阻止しようとするが------。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
相棒の女性刑事パム・グリア(クェンティン・タランティーノ監督の永遠のマドンナ)も危険にさらされるが、最後には真相を知った上院議員を抹殺しようとするヘンリー・シルヴァ一味を壊滅させて一件落着。
お話のお膳立てはものものしく、家庭愛の場面なども盛り込まれ、セガールが得意の日本語を使ったりしてニヤリとさせられるが、全体的に作品自体にまとまりがなく、アクションシーンも期待したわりには盛り上がりに欠けていたと思う。
それでも、最近のふやけた体で粗製乱造する作品群に較べたら、ずっとましな出来栄えですが。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
この映画「刑事ニコ 法の死角」は、我等が危ない親父スティーヴン・セガールの映画デビュー作だ。
全米屈指の犯罪地帯と言われるシカゴで、誰よりも突出した起訴件数を誇る敏腕刑事ニコ・トスカニーニ(スティーヴン・セガール)。
この映画は、元CIAの特殊工作員として戦場に潜入した体験を持つ彼が、日本で身につけた合気道を武器に、政界をも巻き込んだ巨大な麻薬組織に挑んでいく姿をダイナミックに活写している。
主役のスティーヴン・セガールは、この映画の原案・製作も担当していて、実際に合気道の黒帯6段であり、ショーン・コネリーらのハリウッド・スターのコーチも務めたほどの武道の達人なのだ。
ヴェトナム戦争時代に、仲間のヘンリー・シルヴァ(一度、顔を見たら忘れられない程の残忍な顔をした性格俳優)の残忍ぶりを見て、職を辞任するというプロローグの後、シカゴの鬼刑事になった彼が、麻薬事件を捜査していくうちに、CIA絡みの中南米謀略事件にいき当たる。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
日本の俳優陣では、渡辺謙が達者な英語を披露して、さすがという感じで、また、桃井かおりもいい味を出していましたが、役所広司だけは英語も全くダメ、演技もダメでしたね。
これでは、役所広司は今後、ハリウッド映画からのオファーは来ませんね。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
残念ながら、主役のチャン・ツィイーのさゆりに、まわりを圧倒するような存在感がないのだ。
不思議な瞳を持つという設定も生かされていないし、男を虜にする美しさと芸と色気も十分に描かれていなかった気がする。
そのために、彼女の一途な恋愛も「あ、そう。」という感じでしか観ることができなかった。
「芸者は娼婦ではない」のが事実であったとしても、芸者は武士のような、ある種の美学を体現する存在ではないのだ。
芸者の世界には詳しくないので、色々と勉強になったが、千代が神社にお参りするシーンで、どう見ても伏見稲荷という鳥居をくぐって、お賽銭を投げて鈴を鳴らすところで「ゴーン」と鐘の音がしたのには、ずっこけてしまった。
というわけなので、どこまで考証が確かなものかも、正直いってよくわからない。
そして、着物の着方がまことに雑で、興醒めしたが、映像はとても美しく、それほど退屈はしなかった。
しかし、面白かったかと聞かれるとそれほどでもなく、つまらなかったのかと言えば、それほどでもないという微妙な感じの作品でしたね。
- 評価
- ★★☆☆☆
- 投稿日
- 2024-06-28
ロブ・マーシャル監督の「SAYURI」は、貧しい漁村から口減らしのために売られた少女が、花街で一番の芸者になるという、女の一代記。
日本を舞台にした作品だが、原作も映画化したのもアメリカ人。
「ラスト・サムライ」と同様、ハリウッド製和風ファンタジーといったところだ。
日本人キャラが、みんな英語で会話するのも、中国人女優の芸者姿も、心配したほど気にならなかった。
しかし、観終わった後の感想はというと、「それで?」と言うしかない。
さゆりの生き様や芸者の世界のしきたりを描くことで、一体何を伝えたかったのだろうか。
千代が花街に売られてきて、さゆりという芸者になり、ライバルの初桃と壮絶な置屋の後継者争いをするところは、絢爛な世界の裏の女のドロドロとした姿を描いていて、退屈しない。
初桃を演じたコン・リーは、憎まれ役を見事に演じている。
ところがコン・リーが姿を消すと、火が消えたように画面が寂しくなり、映画も失速していく。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
昂まる悲痛のメロディは、やがて、あの光と影の青春の庭、テニス・コートの白い若者たちの優しさに溶け込んで、かき消える。ヴィットリオ・デ・シーカ監督の抑制のきいた演出が、数十年の歳月を経た、ある"時代"への青春の哀歌を静かに謳いあげるのです。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
けれどミコルは、ジョルジョが自分と同じ運命共同体であることを、本能的に察知していたのだ。ユダヤ人の現在と未来に忍び寄る"死の影"を予知して、だから、彼女が愛したのは過去、いとしく甘美で神聖な、幼い日の幻影だけであったのだ。
次第に吹き荒れるナチズムの嵐は、ユダヤ人家族から平和を幸福を、人権を財産を、そして愛を青春を、奪っていくのだ。
はじめはテニス・クラブや図書館からの追放といった差別は、やがて強制逮捕となっていく。
もはや、コンティーニ家の人々といえども例外ではなかった。
ミコルと近親相姦の匂いさえ漂わせた、病的な弟アルベルト(ヘルムート・バーガー)は、高熱にあえいで病死し、彼女が絶望的な愛を結んだコミュニストのマルナーテ青年は、ソ連戦線に召集されて戦死してしまう。
そして、両親と引き離されたミコル。息子たちと妻を逃がしたジョルジョの父。彼らの行く手に待っているのは、収容所であり、死であった。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
親しみを込めて、まるで恋人のように振る舞いながら、だが彼女はジョルジョの求愛をはぐらかし拒絶する。
そして、ついに彼は見てしまうのだ。
ミコルが、彼女の弟アルベルトの親友であり、ジョルジョの心の友ともなったマルナーテ(ファビオ・テスティ)と結ばれた現場を。
こんなふうに荒筋だけを追っていくと、ありふれた青春の失恋のドラマになってしまう。
だが、コンティーニ家も、そしてジョルジョの一家もユダヤ人である。
その宿命の重みが、一九三八---四三年という時代と相まって、哀絶の調べを奏でるのだ。
同じユダヤ人だが、コンティーニ家は"特別"であった。
ジョルジョの家も、かなり裕福だが、大地主コンティーニ家はケタ外れのブルジョワであり、同時にその貴族性のゆえに、彼らは町のユダヤ人社会からも孤絶した、別世界の"異人種"だったのだ。
ユダヤ人の自意識を持つジョルジョが、ミコルに強く惹かれたのは、彼女がユダヤ人らしからぬユダヤ人であったからだろう。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
それは、コンティーニ家の娘ミコル(ドミニク・サンダ)の、ほとんど気まぐれといっていい"招待"によるものだった。
夏の終わり、というより、むしろ秋色濃い日であった。
町のテニス・クラブの若いメンバーたちと、はじめてミコルに呼ばれて、彼はコンティーニ家のコートでテニスに興じるのだった。
そして、その日から、ミコルとの交際が復活した。彼女は、昔と変わらぬ好意を見せるのだった。
そして、昔の思い出を懐かしむのだった。
二人は幼馴染であった。といってもミコルは、町の学校に通学しなかった。
自宅研修生として、年に何度か、試験の時に学校に姿を現わすだけだった。
馬車に乗ってやって来る、この小さな王女さまへの憧れ。
教会での出会い。じっと自分に注がれた彼女の視線を、あの胸のときめきを、今もジョルジョは忘れない。
そうした幼い日の回想の断片が、透明な美しさでよぎるほどに、ジョルジョは、ミコルへの愛の想いを切なくかきたてられるのだった。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-28
"ヴィットリオ・デ・シーカ監督の抑制のきいた演出が、長い歳月を経た、ある時代への青春追想の哀歌を静かに謳いあげた 「悲しみの青春」"
抑えに抑えて、だが、切なさあふれるばかりの青春追想のエレジーである、「ふたりの女」「ひまわり」の名匠ヴィットリオ・デ・シーカ監督が描いた「悲しみの青春」。
原作は、ユダヤ系のイタリア人作家ジョルジョ・バッサーニの小説「フィンツィ・コンティーニ家の庭」で、その原作は、ヒロインのミコルに捧げられているから、これは明らかにバッサーニ自身の物語であろう。
最初に字幕が出る"フェルラーラにて、一九三八年---四三年"。北イタリアのエミリア地方のフェルラーラは、中世の城壁に囲まれた"美しい墓"のような町だ。
その町の中に、さらに孤立するかのように、果てしなく続く堀をめぐらせて、フィンツィ・コンティーニ家の広大な庭と屋敷がある。
青年ジョルジョ(リーノ・カプリッキオ)にとって、コンティーニ家の庭は、幼い頃から憧憬であり恐れであり、光であり、触れ得ざるものであった。
彼は十年かかって、やっとこの庭に立ち入ることを許されたのだった。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
ここで、四人は砂金を分けようとするが、ダッチマンの阻止と彼らを革命の英雄と持ち上げる村人の歓呼に、あっさりと砂金はおろか報酬金まで彼らに提供してしまうのだ。
これはいかにも"アメリカ映画"的で、こんなことは初期から黄金期のマカロニ・ウエスタンでは考えられない行為である。
この作品の公開が、1969年であることから、マカロニ・ウエスタンの変質がうかがえると思います。
尚、メキシコの将校役として、ジャコモ・ロッシ・スツアルトが顔を出しているのは拾いもので、丹波哲郎は「野獣暁に死す」の仲代達矢に続いて、イタリア西部劇に出演した二番目の日本人スターということになり、"サムライ"という役名で、無口な役柄で刀を振りかざしての活躍はまさに、"日本人ここに在り"を示していたと思います。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
そして、出演俳優は、TVの人気ドラマ「スパイ大作戦」のリーダー、フェルプス役で有名なピーター・グレイブス、ジェームズ・ダリー、バッド・スペンサー、ニーノ・カステルヌオーボ、そしてわが日本の丹波哲郎。
丹波哲郎の外国映画への出演は「太陽にかける橋」「第七の暁」「007は二度死ぬ」に次いで4本目の出演作になる。
物語は、この五人が、メキシコに列車で運ばれてくる砂金を奪い、革命軍に寄与するというもので、リーダーのダッチマン(ピーター・グレイブス)に報酬1,000ドルで雇われる"サムライ"(丹波哲郎)は、剣と手裏剣の名手、ジェームズ・ダリーは、爆薬専門の脱走兵、バッド・スペンサーは、牛泥棒にして鉄道の線路の操作がうまく、ニーノ・カステルヌオーボは、身の軽さが身上というプロたち。
各々がそれぞれ特技を持っているのは、「荒野の七人」にもみられるように、この種の映画のお約束のパターンになっている。
五人は革命の闘士を処刑しようとしていた兵隊たちを皆殺しにしたり、いったんは捕まるものの、村娘の機転で脱走に成功し、列車を奇襲して目的を達するのだ。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
もちろん、もうひとつの背景としては、日本側が香港映画の活劇、カンフー映画などへ、その買い付け方針を変更していったということもあるが、1970年代以降の日本公開のマカロニ・ウエスタンは、その大半がアメリカのメジャーの配給会社によるものであることは注目していいように思われます。
アメリカは過去にもすでに、やはりイタリア映画に資本投下をして、史劇を送り出したことがあるが、かくて歴史は繰り返されていくのだ。
そして、出演者たちも、もうハリウッドで食いっぱぐれたセコハン・スターたちではなくなり、現役の人気も知名度もあるスターが駆り出され、作品のセールス・ポイントになっていく。こうして、マカロニ・ウエスタンのアメリカ化、国際化が始まっていったのだ。
さて、この「五人の軍隊」は、「サスペリア」などのイタリアの鬼才監督・ダリオ・アルジェントが脚本に参加している一編だが、MGMの配給で監督はアメリカの俳優出身で「荒野の愚連隊」や「第十七捕虜収容所」などに出演し、その後、監督に転じて「新・猿の惑星」や「オーメン2/ダミアン」や「ファイナル・カウントダウン」を監督したドン・テイラー。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
「荒野の用心棒」「夕陽のガンマン」などのマカロニ・ウスタンを撮った、セルジオ・レオーネという世界的に通用するマカロニ・ウエスタンの監督が誕生し、この監督がクリント・イーストウッドやロッド・スタイガーやチャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンといった本場アメリカの有名俳優たちを次々と起用し、作品も興行的に成功したことから、このイタリア製西部劇のマカロニ・ウエスタンは、単なるイミテーションから、それ自体のものとして認められたとも言えるのだ。
こうして、1960年代後半から1970年代初期にかけて、アメリカは進んでマカロニ・ウエスタンを買い付け、その英語版を世界に配給し、あるいは資本を投下して製作に関わっていくことになる。ロケ地は、スペインの荒野や山岳丘陵地帯、スタッフ、キャストにイタリア人やスペイン人を使うという按配だ。
これは、日本におけるマカロニ・ウエスタンの配給が、それまでもっぱら、東宝東和や日本ヘラルドといった邦人系の配給業者によっていたものが、1970年を境にアメリカのメジャー会社にとって代わられていくことでも如実にうかがえる。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
この「五人の軍隊」は、殺しと流血の暴力描写で全世界で一大ブームを巻き起こした、マカロニ・ウエスタンの痛快娯楽作ですね。
イタリア製西部劇の"マカロニ・ウエスタン"は、まがいもの、殺しと流血の暴力礼讃映画だと言われながら、本場のアメリカ映画界において、正当派の西部劇が衰退していく中で、その存在価値を全世界に広めていったのです。
映画は娯楽で、ましてや、それが西部劇ならば、派手なドンパチに残酷のスパイスをたっぷりふりかけたマカロニ・ウエスタンは、イタリア映画の重要な海外マーケットである中近東や南米、アフリカ諸国の他、本場のアメリカにまで拡散し、この国の貴重な外貨獲得の手段になったのだった。
そして、商売になるとわかったら、なりふりかまわず突き進む、イタリア通俗娯楽映画の真骨頂がここにあるのだと思います。
アメリカで言うところの、"スパゲッティ・ウエスタン"という言葉には、もの珍しさと蔑称のニュアンスが込められている気がしてならないのだが、アメリカも、その存在をもはや無視できなくなってきたことは時代の流れ、趨勢でもあったのだろう。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-28
文化放送(ラジオ)の「くにまる食堂」にて、試写を見たパーソナリティ二人が紹介していたのを聞き、観ようと思いました。
その言葉のとおり、最後の20分ほどは涙が溢れて止まらない感じになりました。あまり多くの映画を見てはいないのですが、これまで見た中では涙の量が一番多かったと思います。
でも、観た後は、「素晴らしいものを見せてもらった」という爽快感でいっぱいになりました。
おそらく、監督さん、出演者、関係者の「ふるさとへの愛」で貫かれている作品だからなのかなと思います。
皆さんに心からの「ありがとう」、「おめでとう」をお伝えしたいです。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-28
すっかり、青年の復讐をとげる物語かと思っていましたが、
何々、スナイパー、工作員並の人物。
隠蔽工作が解かれ、明らかとなった、ケネディ大統領暗殺の全貌。
60年も経てば、関係者もほぼ他界、ヨーロッパでもかなり変貌を遂げたポーランド、その内を開示しても問題はなくなったのでしょう?
スパイ、工作モノの要素が強く、少しラブロマンスで濁していますが、フィリップが、賢くて強く、スナイパー並の腕前と立ち居振舞い。
果たして、彼は、単なる復讐者なのか?
自伝的なら、この作品は、後々の様々な映画の題材となったでしょう?
そのネタ元だからと言う落ちなのかも知れません?
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-28
草笛光子さん
佐藤愛子さん
どちらもめでたい、ご長寿。
幸せの波動を分けてもらえます。
私は、半分位しかですが、
本の内容、映画のストーリーに、驚く程共感する点がありました。
保育園反対のお話なんかは、エピソードの数々に少し価値観が似ていて、
誰から教えてもらった忘れましたが、
「本当に働いている人は働いている様に見えない」
と言う言葉が小学生の頃から頭の片隅にあり、普通に生きる大切さを大切にしています。
つくづく、普通に生きることは、世間では難しく考えている様です。
普通に仕事をすればいいものをことさら主義主張ばかりで、肝心の仕事はそっちのけ、
無為自然、ことさら騒ぎ立てなくても、自己アピールしなくても、なるようになる。
心がすぐ他人の意見に振り回され、スマホ片手に外にばかり向いていて、自分の中が常に不在中。つい、余計な言動に走る。
自然の運びの様な生き方をすれば、収まるところに収まる。
お二方の、老先生は、
その生きる姿勢が、老子(先生)の無為自然に通ずるのかも知れません?
- 評価
- ★☆☆☆☆
- 投稿日
- 2024-06-27
サッカー日本代表が来ても勝てない。プロなのに素人なみの腕前だ、観ていてつまらない。