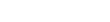- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-01
この映画を観て、とても感動した。これは何よりも人生、人間、愛という永遠の命題を見事に追求しているからだ。お天気キャスターと言えば、今朝、たまたまあるテレビ番組を観ていたら、林佑香さんというお天気キャスターが出演されていた。とびっきりの美人で、目が覚めてしまった。そして私はまたこの映画を思い出した。やはりひじょうに奥深い作品だと思った。こんな映画はほんとに何度も観たほうがいいと思う。素晴らしい作品だ。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-30
素晴らしい作品。
ラストの杏の表情!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-30
この映画を観て、とても感動した。これはあまりにも面白くて、決して飽きさせない魅力があったからだ。クラブと言えば、私は40代の頃は夜の世界にいたが、外国人さんの多いナイトクラブによく行ったものだ。今はもうないが、サムアンドデイブというエンターテイメントバーである。それだけにこの映画はひじょうに関心があった。この映画を観ていると、悪魔的な世界に魅了される自分を発見することになった。とてもインパクトがあって、いつまでも脳裏に焼きついて離れない。素晴らしい作品だと思う。
- 評価
- ★★☆☆☆
- 投稿日
- 2024-06-30
都市伝説で人肉は脂が多く臭くて硬い、喰えたもんじゃないといわれているが、いろんな野菜、果物、肉類、魚介類などを食べてる人間は、ごく美味しいらしい。でもそれを公表すると、食べようとする者が現れるので不味くて喰えないと言っている。人間を襲って食べたクマは味を覚えて人間だけを襲うようになるらしい。みなさん、気をつけましょうね。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-29
演技がすばらしかった!予告編で泣ける話と分かっていましたが、思ったより次々と色んな出来事があり、病気の犬と旅するのは無謀だと思いましたが、何もしないでいるより幸せだと最後には感じました。余韻がいつまでも残る、忘れられない作品です。
- 評価
- ★★☆☆☆
- 投稿日
- 2024-06-29
元ネタは知っていたので期待したけど、違うところが多い。それと主人公の演技がヘタで、違う意味で怖かった。双子の姉妹と川崎麻世さんはよかったです。「きさらぎ駅」のほうが全然ましでした。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-29
この映画を観て、とても感動した。私は昔、シンガポールの日本人学校で日本語教師になりたくて、日本語教師の勉強をしていたことがある。それだけにこの映画はひじょうに関心があった。これはあまりにも面白く、決して飽きさせないストーリーだからだ。素晴らしい俳優陣だと思う。橋幸夫さんの歌も大好きで、今でも印象に残っている。これはまた観たくなる作品だ。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-06-29
黒沢清は、やはり面白い!どんな原作、脚本を監督しても、黒沢清の映画は、黒沢清です!今年は、もう一本新作があると聞きます。楽しみだす!
- 評価
- ★★★☆☆
- 投稿日
- 2024-06-28
寺島しのぶさん、大西信満さんがとにかく素晴らしい。でも内容はあまり響かなかったかな。最後の元ちとせさんの歌のほうが衝撃でした。戦争は愚かな事やというのは伝わりました。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
それまで冷たく見つめていたヴェテランの父も、やっと重い腰を上げるのだった。
そして、その後のビルのスローガンは、対立候補が掲げていたものとそっくりになっていくのだった。
結局、最終的にビルは選挙に勝利するのだが、選挙参謀に向かって「これからどうしたらいい?」と、不安げに言うのだった--------。
高い理想を持って政界に乗り込もうと意欲満々だったビル・マッケイ。
しかし、建前論ばかりの選挙のメカニズムに取り巻かれ、自分が単なる操り人形にすぎないと知ってしまう------。
アメリカ的な成功物語をシニカルに捉えていて、ロバート・レッドフォードが主演ということもあって、爽やかな語り口の青春ドラマ風な仕上がりになっているが、”政治のからくりと怖さの深淵”まで切りこめていなかったのが、いい題材だっただけに、少し残念だ。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
カリフォルニアの上院議員候補として、共和党の現職のジャーモン議員(ドン・ポーター)に対し、民主党ではビル・マッケイ(ロバート・レッドフォード)を立てた。
民主党の長老で州知事も務めたジョン(メルヴィン・ダグラス)の息子という毛並みの良さ、有能な若手弁護士、美しい妻(カレン・カールスン)との理想的な生活、さらに清新なイメージでハンサムな風貌。
ゲームの面白さを捉えることにいつも興味を示すマイケル・リッチー監督は、この作品でも人間の内面を追求することよりも、現代における選挙戦の権謀術数やメカニックなからくりに照準を合わせている。
選挙参謀(ピーター・ボイル)以下、選挙のプロがテレビやPR映画をフルに活用しながら、ビルのイメージを作り上げていくさまが非常に興味深い。
はじめビルは、彼らが狙うままに、対立候補の現実主義に対抗した主張を繰り広げていくが、テレビでの公開討論において、選挙参謀の作戦を無視した発言をやってのけ、それで形勢が不利な状況を逆転させてしまう。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
ボンドが空を飛び、トヨタ2000GTが走り回る「奇妙な日本」は、一度も存在したことはないのに不思議な懐かしさすら感じさせます。
そして、ナンシー・シナトラの歌う同名の主題歌は、美しい旋律と意味深で不吉な歌詞になっていますね。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
丹波哲郎扮するタイガー田中の基地が丸の内線の中野新橋駅だろうと、相撲部屋の外が国技館だろうと、東京から神戸まで車で20分ぐらいだろうと、姫路城に忍者がいようと、瀬戸内海に阿蘇山があろうと、細かいことはどうでもいいのだ。
偽装したカルデラ湖の裏側に巨大な火山型ロケット発射基地がドーンとあり、どうだ、これが007だ!!という大迫力の前には小ネタの笑いなど吹っ飛んでしまいます。
007映画なのに、なぜだか日本の東宝映画の匂いがして、今にもキングギドラでも飛んできそうな雰囲気だ(笑)。
日本人キャストの中で、唯一、英語が堪能だと言われていた丹波哲郎(実際は違うらしい。その証拠に後年、シドニー・ポラック監督の「ザ・ヤクザ」のオファーを受けたものの、あまりの英語の長ゼリフに怖れをなして、出演を断ったという逸話があります)は、若林映子や浜美枝らの取りまとめ役に回っていたそうだ。
- 評価
- ★★★☆☆
- 投稿日
- 2024-06-28
この”007シリーズ”5作目の映画「007は二度死ぬ」は、原題が「You only live twice」と言って、イアン・フレミングの原作で、主人公のジェームズ・ボンドが松尾芭蕉の俳句に因んで詠んだ短い詩が元になっています。
意味は「人生を実感できるのは二度だけ。生まれたときと死ぬときと」。
元々の松尾芭蕉の句は、「命二つ生きたる桜かな」。
死と美学が隣り合わせにある日本人の死生観にイアン・フレミングは感銘を受けたと言われています。
ついでながら、酒と忍者とトルコ風呂にも(笑)。
この映画は、製作準備中に主要スタッフが2度も航空機事故に遭遇するなど、不吉な幕開けとなったことでも有名ですね。
国辱だとか、トンデモ映画という文脈で語られることが多い映画ですが、007スタッフは日本人に畏敬の眼差しを持ち、異文化に対して真摯に取り組んでいると思う。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
そして、十朱幸代、秋吉久美子などの女優陣の絢爛さもさることながら、獣じみた精気を発散させる小林稔侍をはじめ、遠藤太津朗、今井健二といった東映の男優が、いいところを見せてくれるのが嬉しい。
ただ、萩原健一だけが、当時、組んでいた神代辰巳監督作品でのイメージが強いせいか、躊躇したりする時に現代風の印象が抜けきれず、違和感を感じさせたのが残念だ。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
思い出の紅葉の宿で、今は妹の亭主になっている昔の男にすがりつき、身もだえし、ついに再び男女の関係になってしまう場面、どうしようもなく抑えきれぬ気持ちがほとばしり出る。
任侠映画の衰退以来、処を得ていない感のあった山下耕作監督だが、戦前の市井を舞台に男と女の物語を堂々と描く姿勢に立って、長大なドラマを少しの空疎さも感じさせずに織り成していると思う。
昭和10年代の高知の町が、くっきりと浮かび出てくるし、当時の空気も見事に再現されているように思える。
そしてそれが、単に歴史の再現にとどまらず、その時代ならではの激しい思いを抱えて生きた女の半生を、観る者にも鋭く突きつけてくる。
要所要所に挿入される夜汽車のショットが、絶妙のアクセントになっていて、久し振りに山下耕作監督の魅力を堪能させられた。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
「鬼龍院花子の生涯」(1982)、「陽暉桜」(1983)、「櫂」(1985)と続いた宮尾登美子原作による”土佐もの”シリーズは、高田宏治脚本、五社英雄監督で作られてきた。
それが、1987年の「夜汽車」は、松田寛夫、長田紀生コンビの脚本に山下耕作監督という顔合わせで作られているが、だいぶ色合いの違うものになっていると思う。
激しさはできるだけ抑えられ、男と女の情感がじんわりと盛り上がり、次第に大きなうねりを起こしていく様子が、さりげなく、それでいて骨太に語られていく。
遊郭を芸者たちがねり歩く描写ひとつとっても、五社英雄監督の演出が、あでやかに着飾った女たちが、集団で移動していくダイナミズムを感じさせたのに対し、山下耕作監督の演出は、踊りのような、さばけた見のこなしで女たちを歩かせ、たおやかな魅力を画面にあふれさせる。
十朱幸代のヒロインは、男まさりの気の強さを見せ、指までつめてみせても、あくまで女だ。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
最初の第1シリーズの「ルパン三世」の音楽を担当した、山下毅雄が、この作品でもラテン・ロックやスキャットを駆使して、1970年代初期の夜のメカニズムを、アナクロ体験させるサウンドの機密性は、実に素晴らしい。
そして、野坂昭如の「マリリン・モンロー・ノー・リターン」も、実にクールだ。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-06-28
ある地方都市にやって、関西系組織のヒットマンがやって来た。
地元の暴力団は、無礼な挑発にも乗らずにいたが、ある夜、ヒットマンは死体で発見される。
誰が殺したのか騒然となるが、真相が判明しないまま、遂に抗争は、意外な事態へと--------。
監督・中島貞夫と脚本・野上龍雄が初めてコンビを組んで、東映ヤクザ映画のガイドラインを確信犯的に打ち壊した、”現代やくざシリーズ”の第5弾が、この「現代やくざ 血桜三兄弟」だ。
組織からドロップアウトした菅原文太、組織に忠誠心で従う伊吹吾郎、組織の最下端で扱き使われる渡瀬恒彦ら、東映のスター俳優を基軸に据えて、小池朝雄のハードボイルド・テイストや、松尾和子の成熟が、この作品の輪郭を形成している。
だが、それらは、荒木一郎の存在感を際立たせるオプションに他ならない。
個性派演技によって造形された、稀代の非モテ系眼鏡キャラ=通称”モグラ”。
真性チキン野郎が、暴力ドラマを制する映画的奇跡こそが、この作品のエネルギーであり、最高の魅惑的な要素となっている。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-06-28
この作品は、前作の「狙撃」より政治的な表現が多くなり、考えさせられる部分は増えているが、その反面アクションシーンは少なくなってしまっている。
また、この三部作の重要な見どころとなる銃器の描写もやや後退している。
それでも、日本海に出現する工作船や米軍基地への自動車爆弾テロなど、極めて時代を先取りしたような題材が取り上げられているのには驚いてしまう。
主人公を演じる加山雄三は、ガバメントを使用していて、「狙撃」からの流れでフォームが実に決まっている。
また、敵側の名優・佐藤慶は、中田製ワルサーP38で、彼との決戦に際して、加山雄三は中田製MP40ブローバックモデルで立ち向かうのが、実にカッコいい。