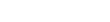- 評価
- ★★★☆☆
- 投稿日
- 2024-07-14
「オリエント急行殺人事件」「ナイル殺人事件」で、アガサ・クリスティー原作のミステリーを、豪華キャストで映画化すれば大ヒット間違いなしというやり方が定着したのか、その第3弾がこの「クリスタル殺人事件」ですね。
しかし、それにしても何とセンスのない邦題なのか。本当に安っぽい題名になっています。
時流に便乗というか何というか、アガサ・クリスティーを愛する一ファンとしては、苦情を言わずにはいられない気持ちになります。
これでは、原作の邦訳名の「鏡は横にひび割れて」のほうが、どれだけいいかわかりません。
いつもセンスの良い、素敵な邦題を付けていた東宝東和とも思えぬ、"悪題"ですね。
それはともかく、今までの2本がエルキュール・ポアロ物だったのに対して、今度の作品はアガサ・クリスティーのミステリーを代表するもう一人の名探偵、ミス・マープルの登場です。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-14
偏執狂患者を暗殺者に仕立てる「大日本人口調節審議会」なる謎の組織に命を狙われた男が、日常品を武器に撃退するアクション・コメディ仕立てで、岡本喜八監督が大いに遊びまくった痛快作だと思います。
主演の仲代達矢のとぼけた三枚目ぶりや、団令子のお色気、がらっ八的な子分役を演じた砂塚英夫に、暗殺団のボス、溝呂木博士を怪演した天本英世など、まさに奇想天外なお話を、キャラクターの掛け合いでグイグイと引っ張る戦略が見事に功を奏し、ダンディズムとモダンが融合した、笑えるハードボイルドになっているところは、岡本喜八監督ならではのうまさだ。
この映画はまた、モンキー・パンチの「ルパン三世」に大きな影響を与えたことでも有名で、スタイル的には都築道夫なのだろうが、峰不二子のルーツは、間違いなく団令子だろう。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-14
この岡本喜八監督のカルト映画中のカルト映画「殺人狂時代」は、面白ミステリーの元祖、都築道夫の「なめくじに聞いてみろ」が原作で、元々、日活が宍戸錠で映画化する予定だった脚本が、巡り巡って岡本喜八監督のところに回ってきたという、いわくつきの作品なんですね。
したがって、活劇路線の日活と岡本喜八監督のテイストが融合した、なんとも東宝カラーに合わない"面白映画"の誕生となったわけです。
ところが、完成された作品が、あまりのカルト性のため、案の定オクラ入りとなって、7,8カ月後にひっそり公開という憂き目にあっているんですね。
とにかく、都築道夫の大ファンを自認する岡本喜八監督としては、キャラクターからディテールまで凝りまくった、モダン・ハードボイルドとも言うべき快作なのですが、時代を先取りし過ぎたところが、理解されなかったのかも知れません。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-14
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
皆を助けるために、進んで海の中へ入っていった科学者が、一瞬の事故から命を落とし、海上に浮かび上がっていき、それを見て、初めて夫への愛を理解する妻のリー・グラントの指には、大きな指輪がはめられていたのですが、あれは、彼女のそれまでの虚飾に満ちた生活が描き込まれていたのだと思うのです。
そしてまた、助かった時、オリヴィア・デ・ハヴィランドとジョセフ・コットンが、しっかりと指と指を絡ませるシーンには、まさに生きている実感が込められていたのではないかと思う。
この大きなスペクタクル・ドラマの中で、小さな指が人間の心を語るなんて、ジェリー・ジェームソン監督はなかなか憎い演出をしてくれます。
そして、一度は助けられながら、また救助に引き返した機長の勇気。
機長だから当たり前と言えばそれまでなのですが、スチュワーデスが震えていた時、彼は言うのです。
「僕も怖い。しかし、我々が助けなければ駄目なんだ」と。
私はここに、人間性を裸にした中での”勇気の真実”を見たように思うのです。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-14
そして、ドラキュラ役者として一世を風靡したクリストファー・リー。
この人は科学者役。彼は実際、大学で教鞭もとっており、大変なインテリ俳優なのです。
その彼を理解出来ずに酒びたりの奥さんが「シャンプー」のリー・グラント、機長を愛するスチュワーデスに「ロングウェイ・ホーム」のブレンダ・ヴァッカロ。
そして、この人が出てくると、必ずジャンボ機は助かるというシリーズのスター、ジョージ・ケネディが、お馴染みのパトローニ役で登場している。
また、乗客の衣装も豪華絢爛で、「ローマの休日」などでアカデミー賞をたくさん受賞しているイデス・ヘッド女史のデザインによる衣装で、もう目を奪われてしまいます。
この作品は、アメリカ海軍や沿岸警備隊の全面協力で、スケールの大きな撮影が可能となったわけですが、その一方で、”人間の指”という小さな部分でも、実に細かい印象的な演出がなされていたと思う。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-07-14
この映画「エアポート’77 バミューダからの脱出」は、「大空港」「エアポート’75」に続く、航空パニック・シリーズの第3弾となる作品。
今回はジャンポ・ジェット機が遭難して、何と海の底に沈んでしまうのです。
しかも、その場所が、あの多くの謎に包まれたバーミューダ・トライアングル。
レーダーにもキャッチされず、無線も届かない。
さあ、乗客はどうなるのか? —-というハラハラ、ときどきする展開となっていきます。
この乗客が様々な人生を背負っているという面白さが、このシリーズの見どころなのですが、しかも、それを豪華なオールスターで描いているところがワクワクさせられるのです。
今回は機長がハリウッド映画界きっての名優ジャック・レモン。
彼はコメディ演技からシリアスな演技まで幅広い芸域を持つ、希代の演技派俳優ですね。
ジャンボ機の持ち主が「グレン・ミラー物語」「裏窓」のジェームズ・スチュアート。
乗客が「風と共に去りぬ」のオリヴィア・デ・ハヴィランド、「第三の男」のジョセフ・コットン—と、懐かしの俳優が顔を揃えていて、嬉しくなります。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-14
山崎賢人が下手すぎてそっちが気になり出して面白くない
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
そして、そのうちの一人、ジャン(ラファエル・フェジト)は、ジュリアンと同じクラスになり、やがて二人の少年の間に友情が芽生えていくのです。
しかし、全ては避けることの出来ない悲劇的なクライマックスへと収束していくことになります。
ルイ・マル監督は、まるでアーチェリーの射手のように、狙いを定め、ゆっくりと弓を引き絞るのです。
そして、ラストの一瞬、矢は放たれ、我々観る者の心を真っすぐに射抜くのです————-。
ルイ・マル監督は、間違いなく彼の生涯で最も重要な、意味ある作品を撮ったのだと思います。
尚、この映画は1987年度のヴェネチア国際映画祭で、最高の作品に授与される金獅子賞を受賞していますね。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-13
フランスのヌーヴェル・ヴァーグの旗手、ルイ・マル監督が撮った「さよなら子供たち」は、戦争が引き裂いた二人の少年の間に芽生えた友情と別離を、感傷に訴えることなく淡々と描いた珠玉の名作だと思います。
この映画「さよなら子供たち」は、1977年以来、創作活動の場をアメリカに移していたルイ・マル監督が、10年ぶりに母国フランスに戻って撮った、”魂を揺さぶる”秀作です。
映画を観終えた後、目頭が真っ赤になっていた自分がそこにいました。
ルイ・マル監督は、かつてなく自伝的色彩の濃いこの作品で、感傷に訴えることを意識的に避けているような気がします。
第二次世界大戦下のフランスで過ごした自身の少年時代の痛ましい記憶を扱いながら、驚くほど抑制の効いた映画を撮ったと思います。
主人公の12歳の少年、ジュリアン(ガスパール・マネッス)は、ルイ・マル監督の分身だと思いますが、このジュリアンは、戦争を避けて、ファンテーヌブローに程近いカトリックの寄宿舎に疎開することになります。
そこに転入生3人が入って来ますが、彼らは実は神父がゲシュタポからかくまっているユダヤ人なのですが。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
東北の雪景色の厳しい美しさ、旅芸人たちの人なつっこい人間味、民衆芸術の生みの苦しみ、そして母もの、夫婦愛ものとしての悲愴なまでの悲しみなど、様々な良さが渾然一体となった秀作だと思う。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
そして、「俺は乞食になる」と堂々と宣言して、実際に乞食に近いような門付け芸の放浪の旅に出る。
その旅は、一面では差別や蔑視を受けた悲惨なものだったが、別の一面では、放浪者らしからぬ自由な明るさと愉しさを持ったものだった。
その旅の中で、新婚の妻を目あきの金持ちに犯される悲惨と、一方では正業に転職した元コソ泥(川谷拓三)や、れっきとした農民でありながら道楽として門付け芸をやっている老人と道連れになるなどの面白いエピソードも描かれる。
しかし、戦争というものは、こんなしがない生活すら放ってはおかなかった。
門付け芸ではやってゆけなくなった定蔵は、マッサージに転業しようとして、盲学校に入る。
そこで、そこの教師にひどい人間的な裏切りを受けたことによる絶望と、それを立ち直らせるための母と妻の献身的な努力が、定蔵を芸術家として更に大きくしていく。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-13
この映画「竹山ひとり旅」は、津軽三味線を一地方のささやかな芸能から、民族的な芸術のひとつにまで押し上げた、高橋竹山の青春時代を描いた作品だ。
竹山の三味線が聞けて、それが素晴らしいことは言うまでもないが、監督・脚本の新藤兼人の演出の腕も冴えわたっていると思う。
若き日の竹山(当時は定蔵)を演じる林隆三、その母の乙羽信子、イタコでもある妻の倍賞美津子など、各俳優たちが小手先の演技ではなく、津軽の雪の重みを感じさせるような素晴らしい演技を体現している。
幼くして視力を失った貧農の子の定蔵は、母が苦労して買った三味線を持って門付けの芸人であるボサマの師匠に弟子入りし、雪の縁側に座って三味線を弾くというような厳しい修行に耐えていく。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
かねてより、クローネンバーグ監督は、善悪の彼岸で死の匂いに浸っていたわけですが、そのニヒルでシニカルな筈のクローネンバーグが、モラルと希望を探している。
実に、皮肉なものです。
かつてのクローネンバーグに比べると、甘すぎると思う人もいるだろうが、ドラマの保守性とかすかなモラルがなければ、生きている意味もないではないか。
暗い映画なのに、久しぶりに救われた気持ちになりました。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
あるいは、トルコ風呂では、全裸の男たちが、ナイフ一本で斬りつけ、殺し合うのだ。
銃ではなく、ナイフに頼るところが、またとても怖いのだ。
だが、この映画は、実はチャールズ・ディケンズの世界だと思う。
闇に包まれてはいるが、モラルが残されている。
起承転結のついた物語を落としどころに持っていく、古風な話法もディケンズそのもの。
ナオミ・ワッツは、邪悪の詰まった箱を開けてしまったパンドラだけど、箱の底にはちゃんと希望が残されているのだ。
非情な暴力とわずかな希望の二重性を見事に表現した、主役のヴィゴ・モーテンセン、実に素晴らしい名演です。
暴力の絶えない世界の中で、倫理はどこに残されるのか。
コーエン兄弟、ティム・バートン、ポール・トーマス・アンダーソンと、優れた監督は皆、このテーマなのだ。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-13
ロンドンの街に広がるロシアン・マフィアの影。
その犠牲となった少女の遺した手記を手にした、助産師ナオミ・ワッツは、産み落とされた遺児の身元を探したために、マフィアに追われる身となってしまう。
全編を通して非常に暗い。ましてや監督は、「ビデオドローム」や「イグジステンズ」など、肉体のグロテスクな変容に取り憑かれてきたデヴィッド・クローネンバーグですから。
何か、とてつもなく悪い予感がしてきます。
ところが、観終わって、後味はそう悪くないのだ。
それどころか、闇に沈むロンドンの片隅に咲いた一輪の花という味わいなのだ。
ただ、そうは言ってもクローネンバーグの映画だから、バイオレンスは、たくさんあって、死体の身元を隠すために、指先を一本一本切り落とす。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
まず、この映画はロードムービーの基本である主人公が、旅に出る理由が、うまくできている。
しかも、父親候補は、市長選の立候補者、結婚式真っ最中の青年実業家、元プロ野球選手、ヤクザの組長の4人。
地域も尾道、別府、長崎、北九州と振り分けられている。これはどう転んでも楽しくなるはずだ。
この映画は、「反マジメ精神」を貫いた前田陽一監督のまさに代表作とも言える作品だ。
父親探しの縦糸に、小夜子が母親のルーツを探す話を絡ませたり、前半で小夜子がエキストラで練習するセリフが、ラストで大きな意味を持つなど、伏線の張り方も巧みで、脚本もよく練り上げられている。
一見、異質に見える主役の二人も、渡瀬恒彦が持つ軽みを引き出すことで、似合いのカップルになっていると思う。
これだけ軽やかに"人情喜劇"を作れた監督なので、生前、もっとたくさんの作品を撮って欲しかったと思う。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-07-13
"ロードムービー"とは、主人公が車や列車などで移動する中で、その過程において様々な人々と触れ合うことにより、人間的に成長していくという映画だが、この前田陽一監督の「神様がくれた赤ん坊」は、まさにこの定義にぴったりな、"ロードムービー"のお手本のような作品だ。
主人公は、エキストラのアルバイトで生活費を稼いでいる同棲中の晋作(渡瀬恒彦)と小夜子(桃井かおり)。
ある日、晋作の子供かもしれないという男の子を押しつけられたことから、この物語は展開していく。
子供の母親は晋作の昔の彼女で、男と逃げてしまったらしい。
この蒸発した母親が「父親の可能性がある男」として、晋作を含む5人の名前をメモに残していたのだ。
「身に覚えがない」晋作は、本物の父親を探しに、子連れで旅に出ることになる。そして、その旅に、小夜子も同行することになって-------。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
主人公のディスクジョッキーに扮しているのは、ロビン・ウィリアムズ。
「ポパイ」を演じ、「ガープの世界」で、我々映画ファンを唸らせた彼である。
うまい、実にいい味を出す役者だ思う。
優しい笑顔の中に、軍の重圧や、不条理な戦争に対する憎しみが込められ、抜群にうまい役者だ。
友と信じたベトナムの青年が、北側の工作員だったことを知った時の彼の哀しみの表情が忘れられない。
なぜ手を取り合って生きていけないのか。
このロビン・ウィリアムズという稀代の役者を起用して、バリー・レビンソン監督は、心に残る名作を撮ったと思いますね。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-07-13
この映画は、ベトナム戦線の兵士に聞かせるラジオのディスクジョッキーのお話ですね。
とにかく、この映画は面白い、たまらなく面白いですね。
米軍の放送だから、検閲も厳しい。その間を縫って、新米のディスクジョッキーは、まあハチャメチャな語りで、兵士たちの心を捉えてしまう。
急激な人気の高まりで、米軍の首脳部は、彼を首にすることも出来ない。
いっそ危険きわまりない最前線へ放り出せば抹殺できると、彼を取材の名目で送り出すのだが----------。
鉄砲玉のように飛び出すブラックジョーク。米軍の検閲制度を徹底的にからかいながら、それでいて若き兵士たちに注ぐ、愛おしみの眼差しは、実に温かい。
激戦地で死んでいくであろう、幼さの残る兵士たち。
主人公の「グッドモーニング・ベトナム!!」という呼びかけの何と優しいことか。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-07-13
黒人の保安官では、町はますます不穏になり、住民たちは土地を捨てて出ていくだろうというのが、知事のねらいで、住民のいなくなったその土地を鉄道会社に売って、ひと儲けしようというハラなのだ。
だが、そうは問屋がおろさない。
バートは、監獄の常連ジム(ジーン・ワイルダー)と意気投合し、知事が送り込んだ無法者タガート(スリム・ピケンズ)一味に立ち向かうのだった。
そして、住民もいつしか二人を信用し始め、協力するようになり、ドタバタ喜劇の定番のパイ投げをやるかと思えば、ターザンが飛び出したり、踊り子のラインダンスが始まるかと思えば、ヒトラーまで派手に登場したりするのだ。
まるでサーカスのどんちゃん騒ぎのような大合戦が、いわば、この映画の見せ場なのだが、このなり振り構わぬドタバタのようで、そのくせ笑いのツボはちゃんと心得ているスマートさ。
まさに、メル・ブルックス監督の独壇場というところでしたね。