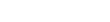- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-12-13
だいぶ前に、日本でも、不食のススメみたいな本が話題になり、その後、世界でも、そんな人々が存在することが話題になり、本からメディア、SNSでかなり浸透しました。
私も、震災後の生活で数日間食べれないことがあり、理解を助けました。
今も、朝は食べ無い方が、好調なので、理解出来るし、日本は、昔は、1日一食かニ食だったのを知れば、さほど、驚かない。
有名な神示の書籍にも、人間は、食べるから死ぬとも、ただ、海山の幸を食べることもススメています。
不食の実践者が存在するから、それも否定できないが、人生は、経験することも大切なので、食べる幸せも大切。
本作品は、ただ、不食をススメる訳ではなく、信仰を食にスポットを当てた、アンチテーゼ。
信じるか、信じないかも、あなたの経験への選択。
キリストのエピソードをモチーフに、復活前の、メタモルフォーゼ。
不食のススメと言うより、人間は、見たいもの、信じたいものを生きる生き物。
食を通し、あなたの生き方は、本当に、信じたものなのか、ステレオタイプの教えに、洗脳されているのかを問う作品。
私達は、宗教を除いても、何かを信じている。
その無意識が、怖いのでありと、
- 評価
- ★★☆☆☆
- 投稿日
- 2024-12-12
youtubeでアニメを途中まで観てたが途中で何か観なくなってリタイアした、そこから月日が流れてて今年総集編で映画化ってなったので、観てなかった続きを観にいったが、ホント相変わらずな脚本、観終わった後に、何故観なくなったか思い出した。ホントに最後の劇場版サンシャインから何も変わってなくて驚いた。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-11
ペンネームに記載した如く、人生で一番の珠玉の作品です。本当に観て良かったと思います、宝物を得たような。最後のカメラシャッター音が温かく大好きです。温かい涙とまた頑張ろうかな、人に優しくしたいなあ、と思える最高の作品。なぜ、小規模上映なのか疑問ですが、皆さん観て感じる映画だと思います。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-11
見てきました 富山で専業主婦は探してもいません まして夫が公務員なら ほとんどが働いてます スナックで市歌が 入り地元民さえ 聞いた事のない歌に 笑ってしまいました 上手な出演者ばかりなのに 残念😢 トルコも もう少し紹介してくださればと 思います 身近な題材ですが 監督の目がもっと輝く作品に なりますように がんばれ👍
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
青年劇場アトリエ上演フィアレス・恐れない人々のリーディング劇を観て居るとミニシュパリズム,地域主義,公共の場等のテーマ性で本篇の区長の姿がオーバーラップ
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
全日本選手権を制し、憧れだった頂点に立ってわずか80数日でのあの落車事故。
辛く長く終わりの見えない日々、森且行を突き動かしたのは、またオーバルでバイクに乗りたい、乗って勝ちたい、この一心でした。
同世代、まだまだ老け込む歳じゃ無いぞ!
もう一度、てっぺん目指して頑張れ!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
テレビ局が作った作品に良い作品無しの定説を打ち破る良作ですよ~お見事!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
リドリー・スコット監督、やりたい放題ですね~デンゼル・ワシントン楽しそうに演じてますね~この二人がこの感じなら言いたいこと無い訳じゃないけど良いですよ~この二人がこの感じなら~!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
凄い役者ですね~阿部サダヲ~いやはや~最初から分かっちゃいるけど凄い役者です!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-10
🕺ジェイウェイブジャストリトルラビング,リビングオンジアースゲストのEXILEUSAダンサーの話題は本篇のキューバの出来事。ダンスは言葉の違いを超え世界の人々を繋ぐと云う。庶民に歓びを齎す祈
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-09
一応の〆、ファイナルに相応しい、締めくくり。
アクション作品と一線を画す、華やかで、スケール感のある医療ドラマ。
虚と実を巧みに織り交ぜ、観客が頭を抱え無い程度に上手く、エンタメと仕上げている。
だいたいの秘められた謎が明かされるが、商業映画なので、僅かに続編への名残りは残しつつ、
巧みな神業のメスさばきの姫(メス、秘め)の大門の演技が凄い迫力で、あのシーンで、見事に泣かせます。
ぜひ、ゆっくり、時間を設けて鑑賞して欲し作品です。
追伸
西田敏行さんに感謝を送り、締めたいと思います。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-09
今朝のNHKラジオ深夜便ロマンチックコンサートはボサノヴァのアントニオ・カルロス・ジョビン特集,映画では黒いオルフェが代表作だが,調べると映画・冒険者等も
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-09
🐴掌小説・川端康成原作の清水宏監督の珠玉作,今朝のNHKラジオ深夜便作家で綴る流行歌・江口夜詩特集,調べると同監督の金環食の映画音楽。放送では十九の春他
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-09
今朝のNHKラジオ深夜便午前4時台恩師を語るでは,タレントのはるな愛が本篇のカルーセル麻紀に就いて人生の師への想いを
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-09
中田絢千ナビゲーターのジャストリトルラビングのリビングオンジアースのguestは本篇エグザイルのダンサーのUSA,祭の国・日本は踊り,ダンサー王国だと云う話
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-08
🌐本篇鎌仲ひとみ監督が絶讃して居るアニメーション映画戦争のつくりかたを平和イベントPEACEActionで視聴。アニーメーターの共同製作のショートショートの力作!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-08
ラジオ日本で紹介された本篇,巨匠監督溝口健二・小津安二郎・成瀬巳喜男へのオマージュと風土の美しき情景が愉しみな印象
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-07
劇場公開から20年、見たかった映画を大きなスクリーンで見る事がで来た、4Kリマスター版、元版はフイルムから修正したもの見たいで、その質感を今のデジタルにない良さを感じる、主演級の豪華キャスト、スタッフによる幾つもの愛の物語、それぞれ愛のエピソードが最後に繋がる、私が気にいった愛の話は、ローラ•リニ-?の片思いしていた彼との思いが叶った時のその嬉しさを体全身で表現する姿が可愛い、妻を亡くしたばかりのその妻の連れ子?養父と義息子、その息子10歳?のはつ恋?を応援する、他に小説家の異文化のメイドへの求婚、笑った、泣いた、後はヒュー•グランドの英国首相は素敵だ、泣いて笑って、見終わった後に優しくなれる映画でした、オススメです。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-06
やっと観れた
友達はウ~ンと言ったが
自分達は満足です
ルシアスを囲む皆最高
あの曲も聴けて涙… 以上
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-06
※このクチコミはネタバレを含みます。 [クリックで本文表示]
迫力があって面白かった