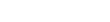- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-17
ダスティン・ホフマンとジョン・ヴォイトがアメリカの夢の哀れな末路を歩む男たちを演じた「真夜中のカーボーイ」。
西部劇のアウトロー気取りで、大都会ニューヨークにやって来たテキサス男のジョーと、都会の底辺で虫けらのように這いずり回る肺病やみのイカサマ師ラッツォ。
ベトナム戦争でボロボロになったアメリカを象徴する二人が、いつの間にかゲイ的な友愛関係を結びながら、常夏のフロリダを目指して、グレイハウンド・バスに乗る。
最後部の座席で死に瀕したラッツォが、小便を漏らすシーンがとても切ない。
皮肉で繊細なイギリス人のジョン・シュレシンジャー監督ならではの、風刺と愛情のこもった映画だ。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-17
復讐するは我にあり、と言う神の法則、森羅万象に働く法則の中で私達は、生きている。
インド映画が大好きで良く鑑賞しますが、アメコミにしては、インド映画に近い作品。
歌やダンスは無いが、因果応報、カルマの法則をベースに展開する。
内容もしっかり、練り込まれていて、若者が多い劇場だったが、最初は、賑やかな雰囲気に心配したが、内容の深さに静かに鑑賞出来た。
ちょっとした、バタフライエフェクト、日頃の他人を小馬鹿にした言動、イジメも含む行為は、自ら撒いた種、いつか、何らかの形で刈り取る。
日頃から、自分の言動には、注意を払い、生きなければいけない。
正に、因果応報のドラマだが、悪因の種は、まだまだ、続く、
続編への為だろが、どう、最終章へ繋げるのかが、楽しみ。
重厚な作品に、ラッセル・クロウの存在が、いいアクセントで、作品のクオリティを高めている。
まだまだ、謎のストーリーがあるので、どう展開するのか、次作も楽しみな作品。
- 評価
- なし
- 投稿日
- 2024-12-17
歴史好きだからレンタルしたけどマジで金と時間を返して欲しい。1時間見てもう限界、見るに耐えない作品だった。人生で見てきた映画の中でマジで1番つまらなかった。この監督、何作っても同じなんよ。結局「このノリ面白いでしょ?」感で身内ウケを押し付けてくる。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-17
今日のNHKラジオ深夜便の作家で綴る流行歌は,作詞家・なかにし礼のPart2,男性歌手特集,本篇の石原裕次郎の場合は我が人生に悔いなし。菅原洋一の今日でお別れ,尾崎紀世彦の5月のバラ,細川たかしの北酒場,北島三郎の祭,黒沢年雄カバー曲をなかにし礼自身のヴォーカルで時には娼婦のように,氷川きよしの桜など深夜に
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-17
佐藤健の、るろうに剣心の剣さばきが観られます。
大河の井伊直政役をやっていた、板垣李光人が、まさかの役どころ。
仲里依紗、この方の一番のカッコ良さが出ていたような。
染谷将太、見るたびいろいろな役が彼の魅力と相乗効果。
山本耕史、阿部サダヲ、小沢真珠、片岡愛之助、いつもの安定キャラに笑える。
こんなコメントですが、納得していただけるかと、、、。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-16
🌕冬空に浮かんだコールドムーンを見上げながら其の言葉の語呂から本篇コールド・マウンテンが,何故か蘇って来たんだなあ
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-16
こりゃあ~あの頃の思い出で生きてる爺にはたまらないアニメです~リメンバー~リメンバー~久々に泣いてるのを隠すために席を最後に立つ~リメンバー~!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-16
🎄今朝のNHKラジオ深夜便午前3時台は郷愁のラジオ歌謡,高英男の雪の降る町をが流れて,アキ・カウリスマキ監督の本篇ラストソングも此の名曲だったと懐かしく
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-16
🥊今朝のNHKラジオ深夜便の片岡鶴太郎の対談相手は本篇のカニング竹山,人生相談員の仕事体験談や何事もトコトン極める鶴太郎のヨガや絵のボクシング等の奥義も
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-16
NHKラジオ文芸館で原田ひ香・作,蒲田・餃子のラジオのリーディングを聴き,本篇や深夜食堂が想い出されて。各地の食文化や其々の人生の味わいが佳かった。上記のドラマでは北海道の帯広市と東京・蒲田が元セールスマンの生命を救った餃子の味から甦る,見守りのシングルマザーの視点で
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-15
これは、カラダの中の「キングダム」だ!
観終わった後につくづくそう思った。
今年1番観たかった映画は、私の期待のさらに上を行く出来栄えに仕上がっていた。
人体は壮大な工場であると同時に壮絶な戦場でもある。毎日毎日細胞たちが生命を維持するために四六時中活動している様がわかりやすくコミカルに、そして、巧みに表現されている。
また、細胞を擬人化することによって秀逸なパロディにもなっている。
笑って、泣けて、学べてしまうスペクタクル大作だ!
今年の最後に、最高の映画が登場したと言ってもいい。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-14
多摩美術大学生涯学習講座世紀の美術で棟方志功,ゴッホの向日葵に魅せられ晩年版画の他,油彩や自画像にも回帰して行く迄
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-14
そして世紀の美術多摩美術大学生涯学習講座バスキアの回,本篇シュナーベルの具象絵画の紹介も有ってストリート落書き論も
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-14
韓国映画はハズレがない、良かった、これが実話と言うのが凄い、実際にあった事件のモデルを元にしたフィクション、事実は本当と言う事なのだろう、女優さん達が素晴らしい、最初は花のないオバさん達に見えたが、ドラマが進むにつれ、輝きだしていく、ドッキと詐欺の若者(監禁されて仕方なくやらされている)との緊迫したやりとり、オバさん達の友情、頼りない警察官を奮い立たせ事件、詐欺のの元締め(悪党)逮捕に導く、元締め(悪党)役の俳優、憎々しくていい、ラスト、詐欺被害者を代弁しての詐欺の元締めとの対峙、対決その勇気に感動、韓国警察、報奨金払ってあげて!
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-14
面白かった、出演者は知らない?ストーリーも最後まで飽きさせる事なく引き込まれて見る事ができた、こう言うホラ-サスペンス?好き、主人公は死なない(勝って終わる)悪い奴は倒される(死ぬ?)映画のラストはこうあって欲しい、異常な家族?リアルに居そう、最後ラストに見せた少年の涙が切ない。
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-13
🇮🇹今日ミーティングでイタリア通の知り合いが長編の本篇を激賞,観たく為った次第
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-13
上田監督は可成の手練になってきた。
そう言えば、内田けんじは何してるのだろう?
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-13
🎩今朝のNHKラジオ深夜便ロマンチックコンサートはチャールズ・チャップリンの映画音楽の特集,マッカーシー旋風下で国外追放された喜劇王の自伝的要素の込められたブラック・コメディの本篇からも音楽が。街の灯,モダンタイムス等の名曲集も
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2024-12-13
様々な演出や展開で、予想を覆して行く、長丁場も、退屈せず飽きさせません。
導入の歌やダンスシーンが、回想や頭を巡らす想像をイメージさせ、映画をよりエンタメに仕上げています。
ラーマ神をモチーフに、七転び八起き、タダでは起きないと言う、インド映画の定番ではあるが、毎回わ新たな解釈、演出で楽しませてくれる作品。
映画なので、エンタメとして楽しみつつ、因果応報を学びたいと思います。
- 評価
- ★★★★☆
- 投稿日
- 2024-12-13
だいぶ前に、日本でも、不食のススメみたいな本が話題になり、その後、世界でも、そんな人々が存在することが話題になり、本からメディア、SNSでかなり浸透しました。
私も、震災後の生活で数日間食べれないことがあり、理解を助けました。
今も、朝は食べ無い方が、好調なので、理解出来るし、日本は、昔は、1日一食かニ食だったのを知れば、さほど、驚かない。
有名な神示の書籍にも、人間は、食べるから死ぬとも、ただ、海山の幸を食べることもススメています。
不食の実践者が存在するから、それも否定できないが、人生は、経験することも大切なので、食べる幸せも大切。
本作品は、ただ、不食をススメる訳ではなく、信仰を食にスポットを当てた、アンチテーゼ。
信じるか、信じないかも、あなたの経験への選択。
キリストのエピソードをモチーフに、復活前の、メタモルフォーゼ。
不食のススメと言うより、人間は、見たいもの、信じたいものを生きる生き物。
食を通し、あなたの生き方は、本当に、信じたものなのか、ステレオタイプの教えに、洗脳されているのかを問う作品。
私達は、宗教を除いても、何かを信じている。
その無意識が、怖いのでありと、