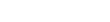評価
★★★ ☆☆投稿日
2024-06-14
どこにも、チャレンジャーを探せなかった。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
そう言えば、後年の2010年にこの映画のリメイク作品である「トゥルー・グリット」(ジョエル&イーサン・コーエン監督)も一種のファンタジーである事を強調して映画化されていましたが、イーサン・コーエン監督も「トゥルー・グリット」の製作意図として、「現代人には非常にエキゾチックに感じられる世界に、14歳の少女が入り込んでゆくという点で”不思議の国のアリス”のような作品でもある」といみじくも語っていたのが、この事を象徴的に言い表わしていると思います。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
三人三様に向こう意気が強く、最初は互いに罵り合っていましたが、旅を続け、共に闘ううちに、お互いの心を開き、やがて本当の親子のような関係になるというエピソードには、ヘンリー・ハサウェイ監督、なかなかやるなという印象を強く持ちました。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
ジョン・ウェインが画面に登場すると、彼の映画の中での過去の異常でダーティな体験が、そのまま彼の体全体からにじみ出ているような男を、勝気で向こう見ずな少女マティが助っ人として雇う映画の最初のシーンに我々観る者は映画的なワクワク感と共に、魅力的な映画の世界にスーッと引き込まれてしまいます。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
彼は1964年頃から、癌と闘いながらタフでたくましい西部の男を演じ続けて来ましたが、今回の1969年の「勇気ある追跡」で初の汚れ役に挑戦して、それを見事に演じきり、今まで過少評価されていた演技力を広く認めさせる事になったと思います。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
“西部劇の大スター、ジョン・ウェインがアカデミー主演男優賞を受賞した記念すべき映画「勇気ある追跡」”
評価
なし
投稿日
2024-06-14
初めて燃えあがった炎を消すまいと、彼女は夫に離婚を迫るが聞き入れられず、パリの親戚に預けられることになる。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
暗闇の中で、青白い炎が妖しく燃えている。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
この味方の連合軍の兵士によって爆破されてしまう”橋”を、戦争というものの無意味さを象徴するものとして、シンボリックに描いたデビット・リーン監督の演出の意図は成功していると思う。
評価
★ ☆☆☆☆投稿日
2024-06-14
この主人公三人の三者三様の軍人気質の葛藤が、この物語の大きな軸になっているが、何といってもジャングルの中での”集団ドラマ”として、そのスケールの大きな展開が、実に見事だ。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
この「戦場にかける橋」という作品は、第二次世界大戦下のタイとビルマの国境近くの日本軍の捕虜収容所が舞台で、この地で日本軍と日本軍の捕虜となった連合軍が、タイ=ビルマ国境のクワイ河に鉄道用の橋を架けるために捕虜たちが動員されるが、イギリス軍指揮官のアレック・ギネスは、ジュネーヴ協定違反だと抗議して従おうとしない。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
デビッド・リーン監督はイギリスの生んだ最も才能豊かな映画監督の一人で、彼の名前を最初に世界的にしたのは、中年の良識ある男女の恋を、落ち着いた緻密な心理描写で見事に描ききった「逢びき」だ。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
このような意味からも、黒澤明がこの映画を撮ったのは、それなりの必然性があったようにも思われます。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
天涯孤独で家も持たず、ウスリー地方の密林の自然と共に暮らしている猟師、デルス・ウザーラ。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
黒澤明の映画といえば、どうしても強い風雨の前での人間たちのギラギラとした争いの場面を連想してしまいます。自然とは黒澤明の映画にとって、実に効果的な舞台背景だったと思う。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
とにかく、ベラ・ルゴシを初めとするエドウッド映画の常連出演者たちというのが、全く”可愛いフリークスたち”と呼びたいような顔ぶれなのだ。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
みすぼらしいスタジオの中で、スタッフの一人が、ライバルのボリス・カーロフの名前を口にした途端、「ファック・ユー!」と激怒するのだが、「アクション!」の合図がかかった途端、コローッと変わって、悲劇的な威厳に満ちた人物になりきる。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
ハリウッド映画界の、一筋のおかしな血の流れ。精神的な血縁関係。
評価
なし
投稿日
2024-06-14
ペラペラと薄っぺらで、安っぽくて、滑稽で、なんだか涙ぐましく美しい。
評価
★★★★★ 投稿日
2024-06-14
この映画「エド・ウッド」は、”史上最低の映画監督”と言われたエド・ウッドの若き日を、彼をこよなく愛するティム・バートン監督が映画化した、非常に美しい作品だ。
全52535件、169/2627ページ