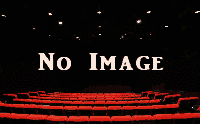広島・八丁座にて先行公開中、8月21日(金)からはアップリンク吉祥寺ほかにて公開となる映画『テロルンとルンルン』より、主演を務めた岡山天音・宮川博至監督のインタビューが到着致しました。
父親が自分のためにつくった花火で事故死したことから自宅に閉じこもるようになった岡山演じるテロルンと、聴覚障害のため学校や家族から孤立しているルンルン(小野莉奈)。そんな二人がある日出会い、窓越しで交流を深めていく中で成長する姿を描く本作。
岡山は人物像やロケセットであるガレージの様子や、コロナ禍における映画の役割などを、宮川監督はCMディレクターとして、本作を製作する上で意識した点や美術へのこだわりなど語っています。
【岡山天音 インタビュー】
◆2018年に自主制作映画として作られた本作のオファーを受けていかがでしたか?
スタッフもキャストの人数も限られていたので全員野球みたいな感覚でしたね。ありがたいことに役者の仕事が増えてくるにつれて、逆にそういう作品に参加できる機会は少なくなっていて。そういった中でこのホン(脚本)と出会えて、その現場に入れるのは本当に嬉しいなと思いましたし、その意味でもモチベーションは高かったです。
◆限られた空間と人間関係の物語から、どのように類の人物像を作り上げていったのですか?
ホンの中の類は、上映時間の中だけに存在している人としてではなくて、ちゃんと生きている人として愛情を込めて描かれていたんです。なので“ホンの美しさ”みたいなものときちんと向き合うことが一番ヒントになったかもしれません。こういう人が現実に生きていてくれたらいいなと思いながら、自分が実際に経験してきたものと重ね合わせていきました。
◆類がその大半を過ごす部屋のロケセットからはどんな影響を受けましたか?
撮影が始まる一日前に現地に行って、類の部屋になっている倉庫に行かせてもらいました。そこで美術を担当された部谷京子さんに、どこに何があるとか説明してもらいながら、実際に椅子に座ってボーッとしたり、いろんなものに触ったり。本当に丁寧に作り込まれていたので感動しましたね。何となくの雰囲気で置かれているものが一つもなくて、一つ一つに血が通っていて、どういう経路でそのものがこの部屋に来たのかが見えてくる。一俳優として、ここでお芝居できるんだと思ってテンションが上がりました。それと同時に、類を演じることに対する気の重さ、考えたくないことを考えなければいけない日々が明日から始まるんだという予感がして、高揚と頭が重くなる感じの両方がありました。
◆あの部屋に引きこもっている類とは演者としてどのように向き合っていたのでしょうか。
類の人生で起こっていることは全て自分の人生の中にもあるものだと思っていたので、類を自分に置き換えることをしていました。類が修理をしている時間はたとえば岡山天音にとってのどういう時間に近いんだろう、類が直面しているものが僕にとっては何になるのか、もしかするとそれはものじゃなくて人かもしれない……とか。壊れた玩具やそれを直す行為を一度抽象化して、自分の中にある記憶とつなぎ合わせる作業は、大事にしていた記憶があります
。
◆たとえば玩具を修理することは、自分のどんな時間や体験に置き換えられましたか?
「母親といる時間」という要素はあったかもしれないです。うちは母子家庭だったんですけど、子供の頃に母親と一緒に部屋で過ごした時間とか。それが類の時間と100%同じ成分かというとそうではないんですけど、類にとって修理中は「安心している時間」である気がしたので、そういう意味で母親との時間に重なるものがありましたね。
◆壊れたものを直す作業は、類が自分自身を再生する行為でもあったのでは。
類の抱えているものやその目に見えているものは大きすぎて、自分とは全く違ったのですが、そこから目を離さずに自分の実感のあるものとして演じなければならないと思っていました。俺自身もとにかく大変で余裕がなかったんです。類という人間に対して誠実に向き合わないと、少しでも目を離した瞬間にわからなくなってしまうような気がして油断できないというか。類と自分とのギャップをギャップのままで終わらせたくない、でもその間の溝は深くて、それを埋めようと必死になっていたんですよね。だから瑠海役の小野莉奈さんともあまり喋れなくて。もしそのテンションに現場全体が染まっていたら作品としてしんどいものになっていたかもしれないんですけど、宮川博至監督は常にフラットで柔らかい居方をしてくれたので、とても救われました。
◆類にとって瑠海との出会いはどんな力になったのでしょうか。
気づいたら自分以外のことを考えていた、みたいな感じですかねえ。それまでの類は自分のこと以外は考えられなくて、その事実にすら気づいていなかったかもしれないけど、そこに瑠海が強引に入ってきて、気づいたら一度も考えたことのないことを考えていた……みたいな。そういう意味で、瑠海は類にとって初めての「他人」だったんじゃないかな。
◆自分以外の人のことを考えることが、自分を救うことにもつながるのかもしれません。映画が終わった後、類はどうなっていくと思いますか?
そこがどうなっていくのか全然わからないのが、この映画の面白さかなと思っていて。終盤の類の行動が次に進む一歩目なのかどうかもわからないし、類も自分でよくわかっていない状態の中で、むしろ結論のようなものを出したくないという思いがあったかもしれないですね。少なくとも何かを予測させるようなところにこちらから誘導することはあまりしたくないと思っていました。予感で埋めてしまうのではなくて、どれだけ余白を余白として残せるかを考えていました。
◆本作で描かれている「外に出る」ことが、今の世の中では別の意味を持ってくるようにも感じられます。
ちょっと大きな言い方になっちゃうんですけど、この世の中には自分以外にも人間がいるということを、楽しんで欲しいなというふうに思っていて。今の時期に公開されるからからこそ特に、外の世界に自分以外の人間がいることが、ふと楽しく見えるきっかけの一つにこの映画がなってくれたらいいなとは思います。
◆映画業界に携わる一員として、コロナ禍の世の中で映画にできることは何だと思いますか?
映画って「ズルい」ものだと思うんですよね。観ると自分以外の人生を味わえちゃう。普段の生活の中ではそういう感じ方はあまりできなかったけど、自粛期間中に久しぶりにたくさんの映画を観て、映画ってそれぐらいパワーのあるカルチャーだと思ったんです。単純に違う世界を知れる、別の世界を垣間見ることもできるし、自分と登場人物を重ねて客観的に自分を見たり、それを反面教師にして生き方を改造したりもできる。あらためてとてつもなくワクワクするコンテンツだと感じたので、実人生を変えるぐらいの湿気や体温みたいなものがスクリーン越しに伝わってくる作品に、また出演できたらいいなと強く思っています。
【宮川博至監督 インタビュー】
◆本作の企画の成り立ちを教えてください。
初監督作である『あの夏、やさしい風』が“SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2015”で上映されたときに、美術監督の部谷京子さんがたまたま観てくださっていて、「次の作品も楽しみにしてるね」というお言葉をいただいたんです。でもその後、1~2年ほどしても何もできませんでした。ですが、部谷さんの言葉が頭の中にずっと残っていて。「何かやらないとまずい……」という焦りもあり、それでいざ腰を上げることになりました。普段僕はコピーライターの方とお仕事を一緒にすることが多く、締めの言葉などを考えてもらうことも多いです。そこで、付き合いの長い川之上智子さんに脚本家として入ってもらい、企画が動き出しました。
◆孤独感を抱える男女の交流を描いた物語ですが、この着想はどのようにして得たのですか?
まず前提として、「ワンシチュエーションで展開する物語にしましょう」というところからスタートしました。そこで、“窓越しに交流する男女の物語”という案が出ました。“引きこもりの青年”、“聴覚に障害がある少女”というキャラクター設定は、川之上さんが意見を出してくれましたね。そこから、瑠海が学校でいじめに遭っているシーンや、類が葛藤している姿を捉えたシーンなどが浮かび、物語が膨らんでいきました。二人でつくりあげていった感じですね。でも、せっかく川之上さんが脚本家として入ってくれているのに、人物設定やそれらを囲む環境についてまで僕があれこれ口を出すので、やりづらかったとは思います。(苦笑)
◆岡山天音さんと小野莉奈さんの組み合わせがとても魅力的でした。
類役に関しては、川之上さんの「岡山さんがいい」という猛プッシュがあり、僕自身も納得でした。瑠海役に関しては、岡山くんのマネージャーさんから「紹介したい子がいる」と、小野さんを紹介していただきました。そんな感じでキャスティングはわりとスムーズで、お二人に会いに東京へ行きましたね。そこで印象的だったのが、岡山くんは演じるキャラクターのことを“とにかく掘り下げて納得したい人なのだな”ということでした。一緒に台本を1ページずつめくりながら、シーンごとの役の感情などについてディスカッションをしました。彼はとてもストイックな俳優です。撮影前にガレージを下見していたようですし、撮影前夜に電話がきたりもしましたね。小野さんは、想像していた以上に幼く見えたのが初対面時の印象です。でも一緒に台本をめくっていると、彼女もまた役について積極的に意見を出してくれて、「あ、やっぱり女優だ」と思わされたのが記憶に残っています。小野さんは岡山くんとはちょっと対照的な感覚派で、その場で生まれた感情に乗って演技をする方という印象です。リハではやらなかったのに、本番では補聴器を投げつけたりだとか。びっくりしました(笑)。お二人とは現場に入る前から、この作品に対する共通認識が持てていたと思います。
◆監督は普段CM製作のお仕事をされていますが、この映画を手がけるうえで意識されたことは
ありますか?
CMの仕事では“最初の波”を意識します。いわばつかみです。観ている方がどこに食いついてくれるのか。この“つかみ”が最初にないと、途中で飽きてしまいます。お客さんの感情の波と、この作品の波が合うかどうか、これをすごく意識しました。基本的にCMは、お客さんが受け身な状態であっても観てもらえるように工夫しています。でも映画となると、お金も払ってもらっていますし、“観てもらえること”が前提ですよね。ですが、せっかくCMで培ってきたものがあるので、これは活かしたいなと思いました。職業柄、観る者を飽きさせないよう、特に“波”を意識しました。あと、塩梅が非常に難しいところですが、説明しすぎないようにしようとは思いました。CMは“説明するもの”なので、気をつけないとこの作品もそうなってしまうだろうなと。それでいて、一つひとつの画に、必ず意味を持たせたいと考えていました。例えば冒頭のシーンで言えば、美しい海と山に囲まれていながらも、この町がとても閉鎖的な空間なのだとあの地形が仄めかすかのように撮りました。
◆舞台である広島の忠海にこだわりはありますか?
窓を中心に物語が進んでいくということがあったので、それ以外に関しては、「気持ちの良い場所でやれればいいな」と思っていました。そこで忠海が見つかりましたね。ここは竹原市というところにあるのですが、過去に竹原市の観光プロモーション映像を撮ったことがあったので、市の方々とも仲良くさせていただいていたんです。しかも、あのガレージを見つけたときは「ここだ!」と。あの町にすべての条件が揃っていました。ちなみにガレージには窓とシャッターはありましたが、劇中に出てくる扉側の壁がもとはなかったんです。そこで美術の部谷さんが、「この辺に大工さんはいない?」とおっしゃって、壁を作ってもらいました。発想のレベルが違いますよね(笑)。
◆本作にはOPとED、それぞれにテーマソングが採用されていますね。
作品の全体の雰囲気としては、日食なつこさんの世界観がこの物語を引き締めてくれると思いました。でも、ずっとエモーショナルな感じを維持するのは違うかなと。なので、類が瑠海にイヤホンを渡すシーンは、あえて日食さんの楽曲ではないものにしました。エンドロールが長い理由は、あのシーンで瑠海が聴くことができなかった、おとぎ話さんの『少年少女』をお客さんにも聴いて欲しいという思いからです。
◆本作は“コミュニケーション問題”を描いた作品だとも思います。
経験上、心に何か傷のようなものがある者同士は、互いに親近感を持つことができるのではないかという考えがあります。なので、環境は違えど孤独感を抱えている二人は、なんとなく分かり合える部分があるのかなと。だからこそ、彼らは言葉がなくても自然と距離が近くなる。はたから見たら分からない、あの二人にだけ通じ合うものがあるのだと思います。