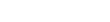P.N.「オーウェン」さんからの投稿
- 評価
- ★★★★★
- 投稿日
- 2025-04-05
このアンドレイ・タルコフスキー監督の「アンドレイ・ルブリョフ」は、「語り始め」の物語だ。
語りかける側の人間が、一度喪った言葉を取り戻し、再び話し始めるまでの物語でもある。
アンドレイ・ルブリョフは、15世紀のロシアに生きた天才的なイコンの画家だ。
中世ロシアの蒙昧、貧困、病苦、戦争-----異民族タタール人に踏みにじられるロシアで、あらゆる世の悲惨をまのあたりにしたアンドレイは、戦いの混乱の中で人を殺し、絵を描くという表現を捨て、沈黙の行に入る。
15年間をその沈黙の中に過ごした後、彼がようやく口を開き、再び絵を描き始めたのは、瑞々しい鐘作りの若者の、表現への狂おしいまでの執着を見たからだ。
語り始めること---表現を取り戻すというモチーフは、タルコフスキーの他の作品では、「鏡」にも見られたと思う。
「鏡」のプロローグには、吃りを矯正される少年の挿話が置かれていたが、あの一見、他の部分とは何の関係もなさそうなシーンが、実は「語り始め」、それまでの強いられた沈黙を破って、表現が復活するという重要なテーマを背負っていたのだ。
沈黙は贖罪のためであると同時に、また、心に残った深い傷跡をも暗示する。
少年時代を第二次世界大戦の只中に過ごしたタルコフスキーの心の傷痕は、「僕の村は戦場だった」の少年の悲惨な運命を描かせた。
異民族の侵入、同じ民族同士の血で血を洗う争いという、15世紀のロシアの現実を映す目は、そのままタルコフスキーの生きた戦中、戦後のソビエトを透視していると思う。
現実に強いられ、あるいは自らに強いた沈黙から復活するアンドレイの姿に、やはり表現者としてのタルコフスキーを重ね合わせることは、決して無理ではないだろう。
戦後のソビエト映画界において、特異な位置を占めるタルコフスキーの、表現への原点とも言うべきものが、この映画には表われていたと思う。