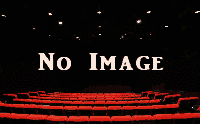2000年にインディペンデントで制作した映画『VERSUS ヴァーサス』で高く評価され、以来、2004年の『ゴジラ FINAL WARS』、2014年の『ルパン三世』と、錚々たる大作映画を手がけてきた北村龍平監督。2007年からハリウッドに拠点を移して活躍している北村監督が、『この世界の片隅に』の真木太郎プロデューサーとタッグを組み、アメリカで製作した映画『ダウンレンジ』が9月15日より日本でも遂に公開される。ハリウッドでアメリカの無名の若手俳優たちを抜擢し、日本の製作会社と共にインディペンデント映画を作るというチャレンジを成し遂げた北村龍平監督に、インタビューを行った。
今回の映画『ダウンレンジ』のストーリーはどのように出来上がったのですか?
■北村龍平監督:『ルパン三世』を監督する前に、この映画のコンセプトを思いついていたんです。エッジの効いたぶっちぎった“ザ・北村龍平”のような映画を作りたくて、どんなものに襲われたら怖いだろうか、と脚本家のジョーイ・オブライアンと話していたんです。それで「戦うことも逃げることもできない、隠れることしかできない状況でスナイパーに襲われたら怖いよね」という話になって。「隠れ場所も車の反対側しかなくて、そこからずっと動かないような映画にしたいよね」「でも、それってすごく難しいよね?」「難しいからいいんじゃん!」と、骨格ができてきたんです。それで、ミニマルなセットアップでマキシマムな緊張感を感じられる映画で、広大な空間にいるのに閉所恐怖症のような、相反する感覚を味わえる作品を作りたいと、今回の企画が固まっていきました。
日本のアニメ会社のジェンコが製作を手がけていますが、製作・企画はどのように進んでいったのですか?
■北村龍平監督:ハリウッドっていうのは、ひとつの企画が動き出して形になるまで、果てしなく時間がかかるんですよ。膨大な契約書をとりかわして、すごく時間をかけて、それでも世に出るか出ないかわからないという世界なんです。それで、そんなめんどくさいことに時間をかけるよりは、もう『VERSUS』をやったような自主映画のスタイルで、志を一緒にできる仲間とインディペンデントでやろうと思ったんですよね。それで、ここが僕のセルフプロデュースのうまいところだと思うんですけど、20年来の仲の良いジェンコの真木太郎プロデューサーに声をかけたんです。普通こういう映画で『この世界の片隅に』のプロデューサーに連絡しないですよね(笑)。
その時は真木プロデューサーは『この世界の片隅に』には取り掛かっていたのですか?
■北村龍平監督:動き出してはいたかもしれませんが、まだ出来上がってもいないし、日本でもほとんどの人があの映画が成功するなんて思っていない時ですよね。でも、真木プロデューサーはすごく振り幅の広い、ハリウッド的な感覚を持っているプロデューサーだと思っていたので、この作品にぴったりだと思ったんです。
それで、この企画が決まった後に『ルパン三世』に取り掛かられたのですか?
■北村龍平監督:山本又一郎プロデューサーから声がかかって、『ルパン三世』の監督をすることになったんですよね。それで2年半くらいルパンにかかりっきりになってしまって。それ以前、7年くらいハリウッドで頑張ってきたわけですけど、その間ハリウッドでのキャリアとしてはブランクになってしまっているんです。「ああ、アイツ日本に帰ったんでしょ?」って思われていたというか。もちろんルパンをやったことに一片の悔いもないんですけど、生存競争の激しいハリウッドでは周回遅れになってしまったような部分もあって。それで、ロスに真木さんが来て一緒に食事をしていた時「龍平ちゃん、そろそろ『ダウンレンジ』やろうぜ」と言ってくれて、再びこの企画が具体的に始動したんです。
本作では無名の俳優を起用していますね。
■北村龍平監督:純粋にビジネスのことを考えると、もっと名の知れた役者の方がいいんでしょうけどね。でも有名な役者を入れてしまうと、ストーリーが予測できてしまいますからね。まったく予測のできない展開にしたかったし、キャストにお金をかけるくらいなら映像にお金をかけたいと思ったんですよ。僕は以前、『ミッドナイト・ミート・トレイン』ではブラッドリー・クーパーを、『NO ONE LIVES ノー・ワン・リヴズ』ではルーク・エヴァンスを無名の頃に抜擢しているんですけど、そういう若い名前の売れてない俳優にもチャンスをあげなきゃいけないと思っているんですよね。それでオーディションの募集をかけたら、こんな小さい作品なのに、1万2千人くらい集まりました。その中から選んだ6人なので、本当に頑張ってくれたと思います。
ブラッドリー・クーパーやルーク・エヴァンスの才能を見抜いて抜擢した監督だということも、ハリウッドでは知られているわけですね。
■北村龍平監督:それはみんな意識していますね。主演のジョディを演じたケリー・コーネアと、エリックを演じたアンソニー・カーリューはその当時演技学校の学生だったんです。演技のうまい人はいっぱいいるけれど、必ずしも演技がうまいだけがいいというわけではないですからね。ごく普通の大学生が極限の状態に追い込まれたらどうなるか、それを表現できるかを重視しました。
余計な説明などが削ぎ落とされた緊張感あふれる作品でしたが、スナイパーがなぜあのような犯行に及んだのか、バックストーリーなどは考えられているのですか?
■北村龍平監督:まったく作っていないですね。実際に事件を起こした銃撃犯の考えていることなんて、わからないじゃないですか?今回、『激突!』『悪魔のいけにえ』『ヒッチャー』なんかの作品を意識したんですけど、これらの映画って、なぜ主人公たちが襲われているのか、まったく理由がわからないんですよね。命を狙われる理由がわからないから怖いんであって、恐怖を描くのにわかりやすい説明なんてなくていいんです。
理由がわからないことが恐怖になるわけですね。
■北村龍平監督:理由は必要なく、とにかく相反するものをすべてつぎ込みたいと思ったんです。ミニマルなセットアップでマキシマムな緊張感、広大な空間なのに閉所恐怖症のような感覚、敵に狙われて車がクラッシュする狂乱のような動の描写と狼が出てくる箇所の静の描写、そうやって相反する部分の描写は成功したと思っています。企画段階でピッチをした時に、スナイパーが襲ってくる理由を入れる必要がある、と言うようなことを言ったプロデューサーもいたんですが、そういうプロデューサーとは絶対組まないと断りました。
ある意味、インディペンデントだからこそ、このような演出も可能なんでしょうか。
■北村龍平監督:映画ってやっぱり膨大な人とお金と時間がかかる芸術なんですよね。そして芸術でありながらもビジネスとしてなりたたなければならない、作家性を貫くことが難しい職業なんですよ。そこに不満を感じているわけではなく、不満があるんだったらインディーズでやればいいと思っているんです。メジャーとインディーズの間でどうやっていくのか、そこの妥協や調整が大事になってきますね。
原作者やステークホルダーの多いメジャー大作では、好きに作るわけにはいかないのですね。
■北村龍平監督:ただ、『ルパン三世』のようなビッグタイトルだから、あれだけのことができたという部分もありますからね。とはいえ、映画作家としてピュアに自分のやりたいことだけをやるというのは難しいです。これまで僕が好きに作った作品をというと、3本しかないんです。好き勝手にやった『VERSUS ヴァーサス』、それで認められてハリウッドに行く前に日本でやりたい放題につくった『LOVEDEATH-ラブデス-』、そしてこの『ダウンレンジ』です。
北村監督というと、やはりインディペンデントで作られた『VERSUS』のイメージが強いです。
■北村龍平監督:いまだに「『VERSUS2』はいつ作るんだ」と言われるんですよ。世界的には、やはり北村龍平の代表作というと『VERSUS ヴァーサス』なんです。まったく知られていなかった北村龍平ががオリジナルでやりたいようにやったあの作品がこれだけ評価されているという。だからこそ、自分がやりたいように作っていけば、世界を熱狂させられる作品ができるんだという自信もあるわけです。そういう部分を真木プロデューサーは見抜いて、『ダウンレンジ』を好きに作ればいい、と言ってくれたわけですよね。真木さんのその読みも当たっていて、海外ではこの作品は北村龍平の最高傑作だと評価されて、僕のこれまでの監督作の中で一番世界的に広がっていますからね。僕自身、世界に向けて認められる映画を作っていくという能力においては、我ながらずば抜けたプロデューサーだと思いますよ。だからこそ、10年以上もハリウッドという魔界で生き抜いてこれたわけでね。
やはり今後も、ハリウッドでの映画制作が中心になるわけですか?
■北村龍平監督:住んでいるのはハリウッドだし、死ぬのもあっちだと思っています。とはいえ、7~8年はやっていましたからね、日本でもやっていきたいとは思っています。個々のスタッフや役者は恐ろしい能力を持っているし、ポテンシャルはまだまだあると思っているんです。一緒にやりたい仲間は日本にもいっぱいいるし、日本でもまだまだやれることはあるなと思っています。映画の仕事というのはタイミングが大事なので、やれるタイミングがあれば日本でもハリウッドでも、他の外国でもやっていきたいですね。
監督が映画を監督するうえで、もっとも大事にされていることはなんですか?
■北村龍平監督:昔から変わらないんですけど、自分の観たいものを作る、ということですかね。自分の観たいものイコールお客さんの観たいものだと思うので、そこはできるだけぶれないようにしたいと思っています。この作品で言うと、ポスターや予告編で“スナイパーに狙われた若者たちが、極限の緊張感の中でサバイブする作品”とうたっている以上は、その通りに極限の緊張感を感じさせる作品にしないとダメだと思うんですよね。それを実現するためのクリエイティビティの戦いはすごくありますよ。エンターテインメント作品として、銃で撃たれるというシーンひとつとっても、誰も見たことのない衝撃的なシーンにしなければならないと、戦っていますから。
確かに、最初の銃撃シーンにも驚かされました。
■北村龍平監督:本当にこだわりましたからね。あの銃撃シーンのイメージを最初にスタッフに説明したときに、みんなどうやって撮るんだと頭を抱えていましたからね。でも、才能のあるスタッフたちがどうやって撮ろうかと必死で考えてくれて、あのシーンが実現しているわけです。でも、そういうワンカットがあるかないかが重要なんですよね。そういうこだわり抜いたカットを10カットも20カットも入れていきたいんです。実際、そういうチャレンジングなシーンを観た観客は大喝采してくれる。お金を払って時間を使って作品を観にきてくれている観客を予測不可能なジェットコースターに乗せて、観たことのない映像で驚かせたいんです。それが僕の戦い方なんですよね。だから、そういう戦いに一緒に取り組んでくれる優秀なスタッフやキャスト、プロデューサーと映画を作っている時は、本当に楽しいですよね。
今作もですが、『ミッドナイト・ミート・トレイン』の殺害シーンも「こんな殺し方があるのか」と衝撃でした。
■北村龍平監督:僕はそんな暴力的な人間じゃないですけど、日々、どういう殺し方をしたら観客に衝撃を与えられるかというのを考えていますからね(笑)。お前は何者なのかと聞かれたら、映画屋としか答えられないんですよ。だからこそ、映画を作ることに関してだけは、真面目に取り組まないといけないと思っているんです。
「ハリウッドという魔界で11年生き抜いてきた」と語る北村龍平監督。世界中から才能が集まるハリウッドという場所で、実績を積み上げ結果を残してきたという強い自信に裏打ちされた言葉の数々が印象に残る。好きなようにとことんこだわって作るインディペンデント作品、原作者やステークホルダーの意見も取り入れながら観客を喜ばせることを重視するメジャー作品、どちらかに振り切るのではなく、メジャーとインディペンデントの両方で才能を発揮してきた北村監督ならではの「映画を作ることに関してだけは、真面目に取り組まないといけない」という言葉に感銘を受けたインタビューだった。
【取材・文】松村知恵美